自閉スペクトラム症の次男の幼稚園生活も3月に無事に終わりました。
あっという間だった気もするけれど、長男の時より心配事も多かった3年間。
普段の園での様子や行事の様子を振り返っていきたいと思います。
入園時(3歳)の次男の状況
まず入園する際の次男の状況をまとめてみました。
・2カ所の療育施設に計3回/週通っている
・食事はほぼ手づかみ(一応使わなくてもスプーンを握っている)
・トイレはまだ出来ないため紙おむつ使用
・下は履けるが上の服は自分では着ることが出来ない
・じっと座ることは苦手
・言葉は多少話せるが要求はほぼジェスチャー
・はい,いいえで応えられる質問以外はほぼ答えられない
例:「今日は楽しかった?」→答えられる 「何が楽しかったの?」→答えられない
・家族以外の前での喜怒哀楽表現ほぼ無し
幼稚園選び
次男の幼稚園は長男の時のように園活してきめたわけではありません。
長男が通っていた幼稚園に次男も通わせることにしました。
それにはいくつかの理由があります↓
2.良い意味で行事などにそこまで力が入っておらず、自由な雰囲気の園だと知っていたから。
3.長男が乗っていた幼稚園バスに次男も乗りたがっていたから。
4.発達障害のある子やダウン症の子など様々な子を多く受け入れている園だと長男の時に感じたから。
園長先生に相談し現在の息子の様子などを伝えたところ、「新たに加配の先生はつきませんが、現在の職員の人数で充分対応できそうなので是非お待ちしています(*^-^*)」と言っていただけて一安心。
不安だらけの入園式

入園式の朝に撮った写真ですが、手が当時息子が不安な時にするしぐさになっています。
本人も親もいつもと違う格好なので緊張している様子でした。
入園式は発達障害があろうとなかろうと、大きな声で話している子や泣いている子もいたりしてとても賑やか。
しかし先生はそんなことは一切気にせずにこやかに挨拶されていました♪
正直ちょっとホッとしました。
息子だけ悪目立ちしたらどうしよう・・・とずっと不安だったもので。
まぁ息子は案の定自分の席には座れず、私の膝から落ちる遊びを繰り返したり、撮影席に座っていた夫の所に何度も走っていったりと自由そのものでした( ̄▽ ̄)

靴下も上履きも履くのが苦手で最初から最後までずっと裸足。
むしろあんな窮屈な恰好をして、良い子に一人で自分の席に座っている子達偉すぎません?
親御さん、本当に褒めてあげて欲しい、あなたのお子さん凄いです👏✨
支援の先生にべったりだった年少さん
年少クラスは1クラス17名に対して担任の先生1人+支援担当の先生1人。
確かに充分手厚く、本当にありがたかったです。
息子には基本的にいつも支援の先生がついてくれていました。
言葉の指示が通りにくい息子にいつもイラストが描かれたカードを見せながら「次は園庭に遊びに行くよ。」などと教えてくれていました。
私が迎えに行く際に少し元気がないだけで、連絡帳に「何か不安なことなどあれば何でも言ってください。連絡帳でもお電話でもいつでもお待ちしています(*^^*)」と書いてくれたりと、息子だけでなく私もかなり救われていました。
息子は何か要求がある時は支援の先生がいないと伝えることが出来ず、担任の先生が「〇〇君どうしたの?トイレに行きたいのかな?」ときいてくれても決して答えなかったそうです。
支援の先生が他の子についてトイレなどに行ってしまい、教室からいなくなるといつもソワソワしていると担任の先生に教えて頂きました。
そのくらい支援の先生が息子にとって安心できる存在でいてくれたようです。
支援の先生だけでなく、担任の先生は勿論、幼稚園全体がいつも優しく見守ってくれているのを感じられて、長男の時以上にこの園で良かったなと感じていました。
それでも息子は困ったことが盛り沢山。
園では家以上に言葉を発しませんし、朝のお集りの時間(5分ほど)は勿論座っていられません。
お友達のことは好きなのですが、上手く接することができず、不安になるとよくロッカーなど狭い所に潜り込んでいたそうです。
確かに3~4歳の次男は家でも不安な時や悲しい時によく狭い所に潜っていました。


心が落ち着くとケロッとして出てくるのですが、おかげで洗濯籠↑は壊れました。
園庭で遊ぶ時間にお迎えに行った時は先生が「〇〇君、お母さんがお迎えに来られたよ~そろそろ出ておいで~。」と狭い隙間に声をかけていて、笑っちゃいけないのですが、人を警戒する猫みたいで可愛いし面白くて🐈
私が「お~い猫くーん。」と声をかけると「〇〇君猫さんみたい(^^)?」とニコニコ顔で出てきました。
トイレトレーニングも幼稚園の先生や療育の先生方のおかげで、年少の終わりにはトイレで出来るようになりました!
出来ることが増えてきた年中さん
年中のクラスは1クラスに対して担任の先生1人+支援担当の先生1人+T.Tの先生1人。
年中さんになってすぐは年少クラスの時の支援の先生を求めていつも年少さんクラスに行っていたようです。
でも年中クラスの支援の先生が「みんな最初はそうですから、ゆっくり見守りたいと思います(*^^*)」と何でもないように言っていただけて親子ともに嬉しかったな~。
相変わらず室内で靴下を履くのが苦手で、裸足で上履きをはいていました。
靴もまだ左右がわかりません。
したい遊びが無い時や気分が高まるといつもロータリーを走り回ってしまう。
お友達が大好きでテンションが上がると友達の上に乗ったり追いかけまわしたりしてしまう。
「もっと遊びたかった」「〇〇君がね・・・」と涙がなかなか止まらないことがる。
「今のは危ないからしないよ!」と注意されると、相手の顔が見れず、最後はロッカーの中に潜って出てこない。
返事をする際に普通に喋ることが恥ずかしいのか、必ずふざけて答える。
制作が大好きですが、作り方など決まりがあるものはしない、自分の好きなように作っている。
大勢での活動は苦手で、教室の隅に机を置き少人数であれば取組むことも出来る。
等々年中でも苦手なことは沢山ある様子。
ですが!出来ることも増えてきました。
まず自分から先生に声をかけることが出来るようになってきました。
幼稚園で泣くことも出来るようになったのは大きな成長です!と支援の先生に言ってもらえました。
お友達の名前を読んだり、たまに一緒に遊ぶようになりました。
苦手な集まりや活動の後は好きな絵本やオモチャで遊べるご褒美タイムを作ってもらうことで、少しずつ我慢も出来るようになりました。
今まで年少・年中で書いていた園での様子は全て先生から教えていただいたことです。
息子は年中さんの途中くらいまでは園での出来事を私には一切話してくれないというか、こちらから、はい・いいえで答えられる質問をしない限り、息子からは何も情報を得られませんでした。
例えば「今日の給食は美味しかった?」には「うん!」と答えてくれても、「何が美味しかったの?」には応えてくれません。
そんな息子が園や療育での成果か成長し、年中の終わりには園でのことやお友達のことなど多く教えてくれるようになりました。

この幼稚園は基本的には絵の時間もいつも自由。
このように下にブルーシートを敷いて、何を描いても何色を使ってもOK!
汚れることも気にせず、思いっきり自由に!みたいなスタイルが次男の特性?性格?には合っていたようで、次男は今でもお絵かきや制作が大好きです!
ただし作る過程で何かルールを決められるのは大嫌い、小学校では苦労しています( ;∀;)
先生よりも友達との関りが増えた年長さん
ほぼ無口だった年少の頃の息子はどこへ行ったのか、5歳になった息子はとにかく賑やか。
いつも大きな声で歌っているし、お友達と遊ぶのも大好き!
今までなぜ喋らなかったんや!?ってくらいお喋り。
長男はどちらかといえば大人しく、お友達と二人で静かに折り紙遊びをしているような年長さんでしたが、次男はいつも元気なお友達とふざけ倒しているTHE男子って感じに仕上がりました、WHY( ゚Д゚)?
それもあってか支援の先生がつくクラスではなく、担任+副担任の先生クラスになりました。
と言っても年長さん全体を見てくれる支援の先生はいます。
息子から得られる情報が増えた一方で、息子にいつもついてくれているような支援の先生がクラスにはいないので、迎えに行った際に得られる情報量がぐんと減りました。
でも小学校入学したらもっとわからないことばかりでしょうし、親も慣れるための1年だと理解しました。
相変わらず朝のお集りの時間はじっと座れず、ぴょんぴょん跳ねていることが多い様子でした。
息子曰く担任の先生も副担任の先生もとても優しいので、給食は残しまくっていた模様( ゚Д゚)コラ!
先生がクラスみんなに話している途中で話しかけたり、途中でわかったと思ったらもう話を聞かなくなるとのこと。
そして勿論全然理解できていない・・・。
クラスの女の子によると、息子はいつもふざけているとのことでした。
こんな顔(´Д`)で教えてくれました(笑)
ごめんよ・・・。
行事での様子
幼稚園で多くの親御さんが楽しみにされているであろう行事。
私も楽しみではありましたが、不安なこと凹むことが多いイベントでもあります。
年少時の運動会。
お遊戯はみんなバラバラでも踊る中、息子は一人下をむいてただただ立ち尽くしていました。
曲の途中の移動も覚えられないのか、先生が連れていってくれるのですが、ふらふらと違うところに行ってしまったり・・・。
練習してはいたのですが、かけっこはスタートがわからず、息子がスタートしないので息子の列だけどんどん順番がずれていき、予め写真撮影用に園が保護者に配っている『〇番目の〇列目』と違ってしまい困られた親御さんが大勢いたはず。
本当に申し訳なくて、私は顔があげられませんでした。
勿論大勢の人がいる中で泣かずに頑張った息子のことは抱きしめてとても褒めましたが、内心はショックで息子が寝た後に泣きました。
園がこれだけ努力してくれても、自分の息子は周りの子達とは同じように出来ないのだとわかってしまった気がして・・・。
しかしコロナでほとんどの行事が無くなり、私は密かほっとしていました。
年中時の保育参観。
猛獣狩りゲームといって先生が言った人数(ライオンなら4文字なので4人)で手をつなぎ座る遊びをすることに。
普段は息子も楽しく参加しているらしいのですが、保護者の方が大勢いて緊張したのでしょうか?
「やらなーい。」と言って大の字で床に寝転がり始めました。
最終的にクラス全員が手をつながなくてはいけないようになっていくゲームなのですが、お友達が「〇〇君来て~。」と誘ってくれても、息子は一向に無視。
せめて教室の隅で悲しそうにしているなら、他の保護者さんも察してくださると思うのですが、息子は教室のど真ん中で大の字で寝転がり、表情も何とも思っていませーんみたいな顔をしていました。
多くの方が息子の事情を知りませんし、「何だコイツ」という目線が凄い・・・。
「参加しなくてもいいよ。」とにこやかに言ってあげるのが正解とはわかりつつも、「ほら呼ばれてるよ、一緒に混ざろうよ。」などと必死に声をかけました。
今思えば息子のためでなく、完全に自分が何もしない親と見られないためです。
最終的に支援の先生などの配慮で全員じゃなくてもOKになったのですが、子供達は納得いきません。
仕方が無いので私が「じゃあおばちゃんを混ぜて~(*^▽^*)」なんて明るく振舞って落ち着きましたが、夫曰くその時の私は完全に涙目だったとのこと。
今ならもう少し上手く立ち回れると思うのですが・・・私も未熟でした。
他にも次はみんなでお外でお弁当を食べましょう♪みたいな時間も、息子はどうしても教室で遊びたがり、移動できませんでした。
そんな息子が少しずつ少しずつ、本人の努力と先生方の支えのおかげで成長し、年中の運動会では踊りは覚えれていないようでしたが、自分で立ち位置をしっかり覚え、移動まで出来ていました!
発表会でも息子の席だけ足跡のマークをつけてもらい、じっと座ることが出来ました。
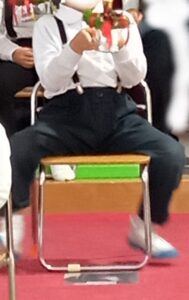
座り方はご愛敬(*´▽`*)
タンバリンもどうにかお隣の子の真似をしていましたし、母は感動しました!!
年長時の運動会。

しっかりと踊っていました。
リズムは全くあっていませんが、2年前は下をむいてただ立っていた息子が楽しそうに踊っていました。
高い所に上る苦手な競技も、事前に担任の先生と何度も練習して、本番もどうにかクリアすることが出来ました👏
卒園式でもないのに涙がとまりませんでした。
保育参観もお友達と楽しく参加出来ましたし、発表会ではセリフもしっかり覚えることが出来ました!
卒園式。
私が異常に泣くので、園児たちがみんな笑っていたなぁ( ̄▽ ̄)
だって本当に様々な思いがこみ上げてきまして・・・。
3年間息子はよく頑張ったと思います。
他の幼稚園では運動会に全員逆立ちや跳び箱を成功させたり、小学生顔負けの合奏をする凄い幼稚園もありましたが、のびのびと頑張らせてくれるこの幼稚園が彼にあっていたと本当に思うと同時に感謝でいっぱいです。
療育との並行通園
息子は週3回療育にも通っていました。
行きはバス、帰りは週三回私が園に迎えに行っていました。
正直せっかく療育に送迎サービスがあるので利用したかったのですが、園が保護者以外の立ち入りを禁じているのでそこは頑張るしかありませんでした。
それも承知でこの園を選んだので仕方がありません。
基本的に療育が好きな息子ですが、給食を食べ終えた頃迎えに行くと、午後も幼稚園が良いと言う時もありました。
幼稚園で楽しそうなことを午後にすると事前にわかっている日は、療育よりも園を優先することもありました。
完全に園と療育施設が連携しているわけではありませんが、園で困ったことは療育に相談出来ますし、園の先生から「~な時はどう対応するのが〇〇君にとって正解なんでしょうか?」という質問があれば、療育の先生にアドバイスをもらうこともありました。
並行通園なんて息子にとっても負担が大きいのでは?と最初は不安でしたが、息子はどちらも大好きでした。
おそらく園は息子にとって良い意味で刺激的な場所で、療育は落ち着ける場所という感じだったのかな?
どちらも私にとっても息子にとっても大切な場所だったのは確かです。
療育については以前の記事でご紹介していますので、よかったら覗いてみてください。
最後に
あらためて振り返ると、息子もそして私も少しずつ強くなってきているように感じました。
大変だったのは確かですが、幼稚園は本当にありがたい存在でした。
私は毎朝バスが見えなくなるまで手を振っていたのですが、全く見向きもしなかった息子が年長の終りごろには私の方は見ずとも、なんとなく手をふってくれていました。
毎朝その姿を見ると頑張るか~と思えた日々でした。
この先の小学校生活を考えると、また不安が押し寄せてきますが、園の先生のようにいつも笑顔でドンと構えていられるお母ちゃんでありたいです。



コメント